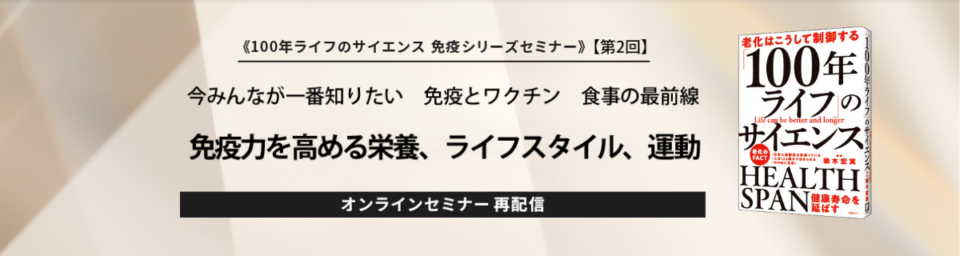筋⾁は、脳からの命令で⾝体を動かす運動器官です。細⻑い1本1本の筋線維が束となって集まっており、年をとるにつれて量や質は低下します。加齢に伴う筋量や筋⼒の低下はサルコペニアとよばれ、転倒や⾻折につながったり、それによる不可逆的な寝たきりを引き起こしたりする因⼦なっています。健康寿命を延ばすためには、このサルコペニアをいかに防ぐかが重要であり、⾼齢者も筋トレをして筋⾁をつけることが大切です。筋力を維持し、アクティブなシニア⽣活を維持できれば、Well-beingの達成が可能です。今回は、筋⾁の仕組みと筋⾁の⽼化についてご紹介します。
Index
宇宙の無重力環境下における筋力低下
普段、私たちの⾝体は筋肉によって⽀えられています。しかし、無重⼒空間では⾝体の重さがなくなるため、筋⾁が使われる機会は地球にいるときと⽐べてずっと少なくなります。筋⾁が使われなくなると、筋⾁のタンパク質を分解する因⼦のはたらきが活性化し、筋線維タンパク質がどんどん壊されていきます。廃⽤性筋萎縮とよばれる現象です。こうして、無重⼒では筋萎縮が進むわけです。宇宙⾶⾏⼠の⽅々は、この廃⽤性筋萎縮を防ぐために国際宇宙ステーションにあるトレーニングマシンで⻑い時間筋トレを⾏います。
加齢とともに筋力はどれくらい低下する?

重力の影響だけでなく、年齢によっても筋肉量と筋力は低下します。75歳以上になると男性では年間0.8~0.98%、⼥性では年間0.64~0.7%の勢いで筋⾁の量が減少します。筋⼒に関してはさらに減少幅が⼤きく、男性では年間3~4%、⼥性では年間2.5~3%のスピードで衰えていくことが報告されています。※1
加齢に伴って筋⾁量や筋⼒が低下する老化現象をサルコペニアといいます。近年、サルコペニアに関する研究が盛んに行われています。サルコペニアを放っておくと⾼齢者の転倒を引き起こす原因となり、転倒によって⾻折してしまうことがあります。⾻折の治療のために⼊院すると、⼀度落ちた筋⾁が元に戻らず、寝たきりの状態になってしまうことも少なくありません。
実際、⾼齢者において、筋⼒は死亡率と逆相関しています。※2
筋⼒の維持が死亡率を低下させているのか、死に近づく⾼齢者の状態の悪さが筋⼒低下を反映しているだけなのか、因果関係はまだ明らかになっていません。⼀⽅で、筋⼒を維持することの重要性は広く認識されています。
では、筋⼒を維持するために、そもそも筋⾁がどうやって増えるのかについて考えていきましょう。
筋⾁はどうやって肥⼤するの?
筋⾁には筋衛星細胞(サテライト細胞)とよばれる、筋⾁特異的な幹細胞が存在します。筋トレでどのように筋⾁がつくのか、詳細なメカニズムはまだわかっていませんが、筋トレによって筋線維が少し傷つくことが、サテライト細胞が増殖するきっかけとなります。サテライト細胞が増殖して筋線維に核を供給することで、筋線維の修復と肥⼤に関与するとされています。※3
サテライト細胞は通常、筋線維とそれを包む膜の間のサテライトポジションとよばれる場所で眠っています。筋トレによって筋⾁が壊れると、このサテライト細胞が活性化して増殖し、筋⾁の細胞へと分化します。分化してできた筋⾁になる細胞を、筋芽細胞といいます。筋芽細胞はお互いを認識すると融合し、1本の筋線維を作ることで壊れた筋⾁を再⽣するといわれています。
筋⾁と幹細胞

上記の画像は、ヒトの筋芽細胞を試験管(シャーレと培地)で実験的に培養したときの様⼦です。最初は1つの丸い細胞ですが、試験管に張り付くと増殖を始め、融合した⼤きな1本の筋線維のような形態を⽰すようになります。

また、こちらの画像は、ヒト筋芽細胞を培養して筋菅細胞を作らせた後、⾚⾊と緑⾊で染⾊したものです。⻘⾊は細胞の核を染⾊したものです。1本の筋菅に複数の核が⼊っています。複数の細胞が融合して1本の筋菅を形成していることがわかります。
Aging Hallmarks 2023の「幹細胞の枯渇」とは

ここまでお伝えしてきたように、筋線維の修復と肥⼤を通して筋⾁の量を増やすためには、幹細胞が重要です。何歳になっても筋⾁を増やすことはできますが、幹細胞⾃体は加齢の影響を強く受けることが知られています。
Aging Hallmarks 2023にも、no.9「幹細胞の枯渇」という項目があります。※4
ここではAging Hallmarksの論⽂をもとに、⽼化と幹細胞の関係について解説します。
Aging Hallmarks no.9「幹細胞の枯渇」に見る⽼化と幹細胞の関係

⽼化は、組織の安定した状態における組織再⽣の減少、および怪我時の組織修復の障害と関連しています。各臓器はそれぞれ独⾃の再⽣と修復の戦略を持っています。例えば、⾻格筋では、再⽣と修復のためにひとつの単⼀細胞タイプであるサテライト細胞が階層の頂点に位置しています。⽪膚表⽪では、⾼い再⽣能⼒と怪我にさらされる特性から、特に⽑包に関連した複数の幹細胞ニッチが存在し、それぞれが⾃らの⼦孫と領域を⽣成します。
しかし、怪我時には、複数の細胞が幹細胞特性を獲得し、領域の境界を乗り越えることがあります。肝臓、肺、膵臓などの他の臓器は通常の状態では再⽣率が低く、異なる細胞タイプによって増殖と多能性を含む幹細胞特性が獲得されます。
実際、組織修復は、⼤部分が怪我による細胞の脱分化と可塑性に頼っていると考えられています。例えば、腸、脳、肺では、怪我により⾮幹細胞が脱分化し、通常は沈黙している胚性と幹細胞性の転写プログラムが再活性化され、組織修復に必要な可塑性を獲得します。可塑性の引き⾦となる怪我による脱分化(および⽼化とともに進⾏するその喪失)は、通常の恒常性条件下における在来の幹細胞の可塑性と比べ、⽼化がより関連する可能性があります。
幹細胞および前駆細胞は、幹細胞能⼒を持たない細胞と同様に⽼化の特徴に影響を受けるため、ここでは⽼化の各特徴が幹細胞機能に及ぼす影響については詳述しません。代わりに、⽼化した幹細胞機能の低下に対抗することを目的とした、「細胞再プログラミング」という概念に基づく⼀般的な戦略に焦点を当てます。
再プログラミングと細胞の若返り
多能性への細胞再プログラミングは、成体体細胞を多能性幹細胞(iPS細胞ともよばれる)に変換することをいいます。再プログラミングには、2012年に京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学・生理学賞を受賞することになった山中因子とも知られているOCT4、SOX2、KLF4、MYC(OSKM)という 4つの転写因⼦の同時作⽤が関与します。再プログラミングのプロセスは通常数週間を要し、細胞はまず細胞アイデンティティ遺伝⼦の転写抑制により分化した表現型を失い、その後多能性遺伝⼦を活性化させます。完全な再プログラミングは、老化細胞で活発になるp16遺伝子の活性減少、老化によって短くなったテロメアの延⻑、DNAメチル化クロックのリセットなど、細胞の若返りとみなすこともできます。※5
興味深いことに、若返りは脱分化開始後すぐに始まり、中間状態でプロセスを中断し、細胞が元のアイデンティティに戻ることが可能です。この⼀時的な細胞の変動、部分的再プログラミングは、in vitroおよびin vivoでDNAメチル化クロック、DNA損傷、エピジェネティックパターン、⽼化関連のトランスクリプトームの若返りなどの⽼化マーカーの消去を実現することができます。
したがって、脱分化と若返りのプロセスは結びついていると考えられます。具体的には、脱分化はエピジェネティックおよび転写プログラムの消去を意味し、これにより⽼化関連の変化も消去される可能性があります。部分的再プログラミングを中断すると、細胞は若返りをリセットせずに元のエピジェネティックおよび転写状態を再確⽴します。
COFFEE BREAK 日常生活に無理なく運動習慣を取り入れる
最後に、とあるNOMON CEOの運動習慣をご紹介します。⽇常⽣活の中で運動量を増やす習慣のひとつとして、参考になれば幸いです。

毎⽇の習慣として、以下を無理なく、できる限り実施しています。絶対守ると決めつけない範囲で取り組むことを大事にしています。
・なるべく1日あたり8000歩以上歩く。
・股関節、⾜⾸、背中などのストレッチ、腕⽴て伏せ10回以上を、朝と夜に実施。
・ピアノ5~10分
・ゴルフ素振り(週1~2回はゴルフ練習場へ、⽉1~2回はゴルフラウンドへ行く)
毎⽇少しずつ運動し、ピアノで指を動かしながら、⽉数回のゴルフでリフレッシュ。運動習慣を何気なく⽇常⽣活に取り⼊れ、楽しむことで、無理のない範囲で運動量を確保しています。
筋力維持のためにはタンパク質の適切な摂取も重要
現時点では、サルコペニアを治療する⽅法は存在しません。⽇々の⽣活でいかに筋⾁を落とさないようにするかが重要です。規則正しい⽣活、バランスの取れた⾷事、⼗分な睡眠と適度な運動が⼤事であることはいうまでもありません。特に、筋⾁の元となるタンパク質に関しては、⾷事から摂るタンパク質量が不⾜しないように注意する必要があります。運動・食事などの生活習慣を整えてサルコペニアを防ぎ、健やかで楽しいWell-beingを実現しましょう。
関連セミナー
参考資料
※1 W. Kyle Mitchell et al. (2012) Sarcopenia, dynapenia, and the impact of advancing age on human skeletal muscle size and strength; a quantitative review. Striated Muscle Physiology, Vol3ー2012
※2 Jonatan R Ruiz et al.(2008) Association between muscular strength and mortality in men: prospective cohort study. British Medical Journal, 2008 Jul 1;337(7661):a439.
※3 William Roman et al.(2021) Muscle repair after physiological damage relies on nuclear migration for cellular reconstruction. Science, 2021 Oct 15;374(6565):355-359.
※4 Carlos López-Otín. (2023). Hallmarks of aging: An expanding universe. Cell, 186, ISSUE 2, p.243-278
※5 Satotaka Omori, et al. (2020) Generation of a p16 reporter mouse and its use to characterize and target p16hight cells in vivo. Cell Metabolism, 32(5), 814-828.e6