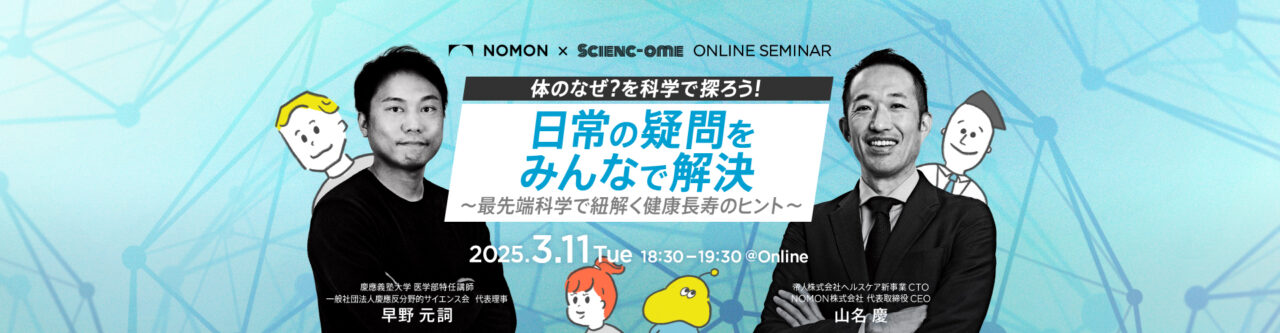「新しいスマホに変えてみたけど、以前に比べて新機能を使いこなせなくなった」「資格の勉強を始めたのに、新しいことをなかなか覚えられない」
こんな経験は誰しもお持ちなのではないでしょうか? 学生時代はいろいろと暗記できていたのに、当時のようには覚えられないことで「自分は年をとってしまったんだ」とがっかりしてしまうかもしれません。
たしかに年をとれば脳は老化し、学習能力が低下すると想像しがちです。しかし、はたして本当にそうなのでしょうか?
今回は、学習効果と老化の関係についてご紹介します。
Index
各能力のピークの年齢は?
記憶力が衰えたからといって脳の機能が衰えているかというと、必ずしもそうではありません。マサチューセッツ工科大学のHartshorne氏によると、言語を学んだり新しいものごとを覚えたりする記憶力や、身体能力の中心となる筋肉の機能は若いうちにピークを迎えます。一方で、計算能力や共感力、語彙力は人生の後半にそのピークを迎え、心身の幸福やウェルビーイングのピークは70歳以降に訪れるとされています。※1
-
- 18歳頃
- 全体的な脳の処理能力と細部の記憶力のピーク

-
- 22歳頃
- 馴染みのない名前を学習できる能力のピーク

-
- 32歳頃
- 顔認識能力のピーク

-
- 43歳頃
- 集中力のピーク

-
- 48歳頃
- 他人の感情を識別するのが最も得意になる

-
- 50歳頃
- 基本的な算数の能力や、新しい情報を学び理解する能力のピーク

-
- 67歳頃
- 語彙力のピーク

何を学ぶのか、その内容によって各年代でピークとなる学習能力が変化しているということです。その変化は、人生の変遷への対応力を生み出す源泉となっているのかもしれません。
加齢とともに知能は低下するのか
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 西田裕紀子先生によると、知能には結晶性知能と流動性知能の2種類があります。※2
- 結晶性知能:個人が長年にわたる経験から獲得する知識。20歳以降も上昇し、高齢になっても安定する
- 流動性知能:新しい環境に適応するために新しい情報を獲得する知識。10代後半から20代前半にかけてピークを迎え、その後は低下の一途をたどる
冒頭で述べたような、新しいスマホの機能を使いこなせない、資格の勉強がなかなか進まないといった状態は、新しいことを記憶する流動性知能が加齢に伴って低下したことが原因と考えられます。一方、結晶性知能は言語能力や洞察力、推察力、理解力、批判および創造などの能力であり、生涯のさまざまな経験を通じて磨き上げることができます。年齢を重ねた後は、結晶性知能を磨き上げることで流動性知能の低下を補い、また全体のパフォーマンス向上をめざしていけるのかもしれません。
西田先生は論文のなかで、2004年に行われたT. Salthouse氏の研究と、2013年に行われたSchaie, K. W氏らの研究を紹介しています。それぞれの研究の概要は以下の通りです。
まず、T. Salthouse氏の研究では、語彙力・情報処理スピード・推察力・記憶力という4つの検査を1,000名以上に対して行い、年代ごとの点数を比較しました。その結果、下のグラフに示すように、流動性知能の指標である情報処理スピード・推察力・記憶力は加齢に伴って低下していたといいます。その一方で、結晶性知能の指標である「語彙力」は20代から60代にかけて増加し、80代になっても維持されていることがわかりました。

Schaie K. W氏らが行った「シアトル縦断研究」においても、結晶性知能である「語彙力」は60代にピークを迎え、緩やかに低下しながらも80代まで概ね維持されることがわかっています。この研究ではさらに、推察力や空間認知力などの流動性知能も、55~60歳頃までは維持されていることが示されています。

また、西田先生は愛知淑徳大学健康医療科学部の安藤富士子教授とともに、12年間にわたる知能の加齢変化についての研究も行っています。「国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」の参加者を対象としたこの研究では、平均年齢59.2歳の男女計2,260名に対し、最長で約12年間の追跡を行いました。その結果、情報処理のスピードは50代後半以降急激に低下するのに対し、知識力は40歳以降も70歳頃まで向上することが示されました。※3
これらの研究により、脳の機能のすべてが加齢に伴って同時に低下するわけではなく、ある程度の年齢までは維持されていることがわかります。
年齢に応じて学習の仕方を変えていくことが大事

脳内科医・医学博士である加藤俊徳先生の著書『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』では、加齢に伴い変化する脳の能力にあわせて勉強方法を変える大切さが紹介されています。※4
脳の仕組みは、若いときはインプット中心ですが、年齢を重ねるにつれてアウトプット中心へと変わっています。したがって、学生時代と同じように、付箋を貼ったり、蛍光ペンで線を引いたりしながら学習しても、アウトプット中心になった大人脳には効果がないといいます。※4
著者は脳の中で部署のような役割を果たす場所を、それぞれの役割に基づいて「脳番地」と名付けました。8つの脳番地の特性を理解し、使いこなすことで、学ぶ力は成長します。※4
- 思考系脳番地
- 理解系脳番地
- 記憶系脳番地
- 感情系脳番地
- 伝達系脳番地
- 運動系脳番地
- 視覚系脳番地
- 聴覚系脳番地
大人になると丸暗記はできなくなる
大人の場合、単純に「記憶しよう」としても、記憶系脳番地は思ったようにはたらきません。何かを覚えたいときは、「覚えよう」とするより、理解系脳番地に任せて「理解しよう」と脳をはたらかせることがポイントです。※4
喜怒哀楽で記憶力がアップする
感情が大きく動くできごとがあると感情系と記憶系をつなぐ脳番地ルートが刺激されて、海馬は重要な情報だと判断します。つまり、エピソード記憶は無条件で長期記憶へと送られる仕組みになっています。※4
その日のうちの復習で記憶の定着率がアップする
脳科学的には、覚えたことはその日のうちに復習するのが鉄則です。また、復習する際には、復習専用のノートを作るのがおすすめです。ノートに要点をまとめる作業には、理解系脳番地、運動系脳番地、視覚系脳番地を使うため、記憶に残りやすくなります。※4
連続性があると、脳はよくはたらく
2時間の勉強よりも、10分間の勉強を12日間続けた方が脳科学的には効率の良い勉強法といえます。視覚系と聴覚系の情報収集力も上げ、勉強している以外の時間にふと目にした情報を取り込んだり、そのことについて考える時間も増えたりします。※4
アウトプットを意識しながら勉強する
例えば、「これから習うものを、明日発表しなければならない」と最初から自分に意識付けすることで、とたんに脳番地たちに緊張感が生まれます。情報を集め(運動系)、見聞きしたこと(視覚系と聴覚系)を理解し(理解系)、考え(思考系)、記憶して(記憶系)誰かに伝える(伝達系)というように、脳番地は一気にはたらき出します。※4
そもそも脳には、情報をインプットするときだけでなく、アウトプットのために取り込んだ情報を思い起こそうとしたときの方がより強く記憶される「出力強化性」が備わっています。そのため、記憶力の向上にもアウトプットは欠かせません。※4
この他にも、脳科学に基づき、年齢を重ねた大人の脳の仕組みにあわせたさまざまな勉強方法が『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』の中で紹介されています。
知能の低下よりも、意欲低下が勉強の障壁に
精神科医である和田秀樹氏の著書『50歳からの勉強法』においても、加齢が学習にどのような影響を与えるのか紹介されています。※5
加齢により知能は低下しませんが、前頭葉の老化と男性ホルモンが低下することで、50代から学習意欲をはじめとするさまざまな意欲が低下しはじめます。※5
意欲の低下は勉強の障壁となるので、以下の方法を参考に防ぐようにしましょう。
前頭葉の老化
前頭葉の老化を防止するためには、前頭葉を使う生活をすることが大事です。同じことを繰り返す生活では、前頭葉をあまり使いません。仕事でも趣味でもよいので、40~50代のうちに、想定外のことが起こりそうなさまざまな体験を意識的に取り入れる必要があります。※5
男性ホルモンについて
男女ともに、欧米ではHRT(ホルモン補充療法)を受けるのが一般的です。ただし、日本では副作用の懸念からほとんど普及していません。受けるかは個人の選択となります。※5
COFFEE BREAK 年齢にあわせた学習方法
最後に、30代後半のとあるNOMON研究員の学習習慣をご紹介します。

NOMONの事業に携わるようになり、研究しかしてこなかったこれまでのキャリアでは仕事の内容に限界を感じるようになりました。ビジネスのことを少しでも知れたらと思い、ビジネスコンサルティングの国家資格である中小企業診断士の資格を取得しようと、勉強を開始しました。
学生時代にも、就職活動のために手をつけたことがある資格だったので、いけるだろうと軽い気持ちで15年ぶりにテキストを開きました。学生時代と同じく、テキストをただ読むだけの勉強方法で、知識の習得を開始したのですが……びっくりするぐらいテキストの内容がまったく頭に入りません。
読むだけではダメだと思い、本屋で問題集を買いました。テキストを暗記するインプット中心の学習から、問題集を使ったアウトプット中心の学習へ変更したのです。
学生の頃と比べて、良くなったこともあります。当時は胆力がなく、長く机に座って学習時間を確保するのが難しかったのですが、今は社会人生活の経験からなのか、1~2時間でも机に座って取り組むことができ、勉強時間は確保できるようになっていました。
また、こちらのNOMON研究員は、寝る前に脳の疲労をとる目的で、6MSITCのサプリメントを飲用することを習慣づけました。6MSITC(6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート)は本わさびに含まれる成分であり、酸化ストレスから細胞を守る効果や抗酸化作用、抗炎症作用があります。疲労の原因である慢性炎症への効果も期待されており、疲労の軽減に役立つと考えられています。
6MSITCの詳細については、こちらの記事もご参照ください。
関連記事:疲労と老化の関連性とは?最新研究や疲労回復・抗老化に有効な栄養素や成分についても解説
関連記事:慢性疲労症候群に対する6-MSITCの効果~最新の臨床研究結果~
サプリの力を借りながら、寝落ちするまでひたすら問題集に取り組む毎日。一次試験は暗記中心の科目でしたが、アウトプット中心に学習方法を変更したこと、勉強量を増やしたことで、学生の頃よりも高い点数で試験を通過することができました。
たしかに若い頃に比べれば、新しい知識を覚えるのに時間がかかるのは事実です。しかし、やり方を変えればしっかりと知識を身につけることができたので、加齢によって学習効果自体が低下しているわけではないのだと身をもって痛感しました。
脳の機能の変化にあわせた方法で学習しよう
加齢とともに脳の機能が衰えていくのではなく、あくまで脳の機能が変化していくだけです。この変化にあわせた学習方法をしていないため、今までのやり方では学習効果が出ないのです。学習効果の低下を脳の老化と決めつけてしまうのではなく、脳の機能が変化しただけだと理解しましょう。そう考えれば、何歳からでも学習を始められるきっかけになるはずです。
いつの時代も新しいことを学び、挑戦し続けることが人生の豊かさにつながります。人生の彩りを豊かにすることでアクティブなシニアライフを送り、Well-beingを追求していきましょう。
参考資料
※1 Joshua K. Hartshorne, et al. (2015) When Does Cognitive Functioning Peak? The Asynchronous Rise and Fall of Different Cognitive Abilities Across the Life Span. Psychological Science, 26(4)
※2 西田裕紀子 (2017) 中高年者の知能の加齢変化. 老年期認知症研究会誌 第 21誌.
※3 西田裕紀子, 安藤富士子
(2013) 厚生労働科学研究費補助金(認知症対策総合研究事業) 分担研究報告書 中高年者の知能の加齢変化:12年間の縦断的検討
※4 加藤俊徳(著). (2022). 一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方. サンマーク出版.
※5 和田 秀樹. (2016) 50歳からの勉強法. ディスカヴァー携書.