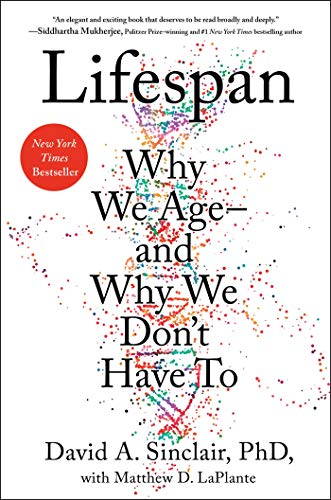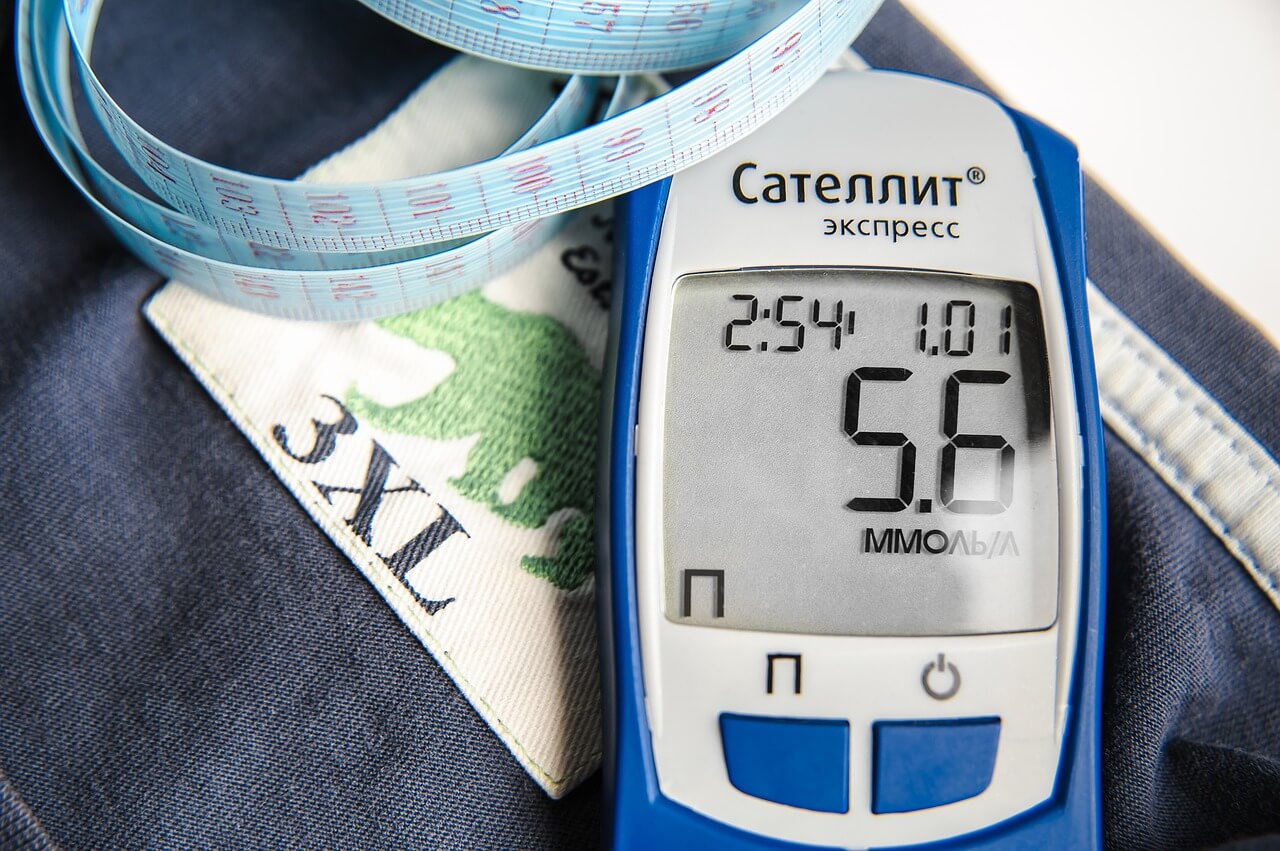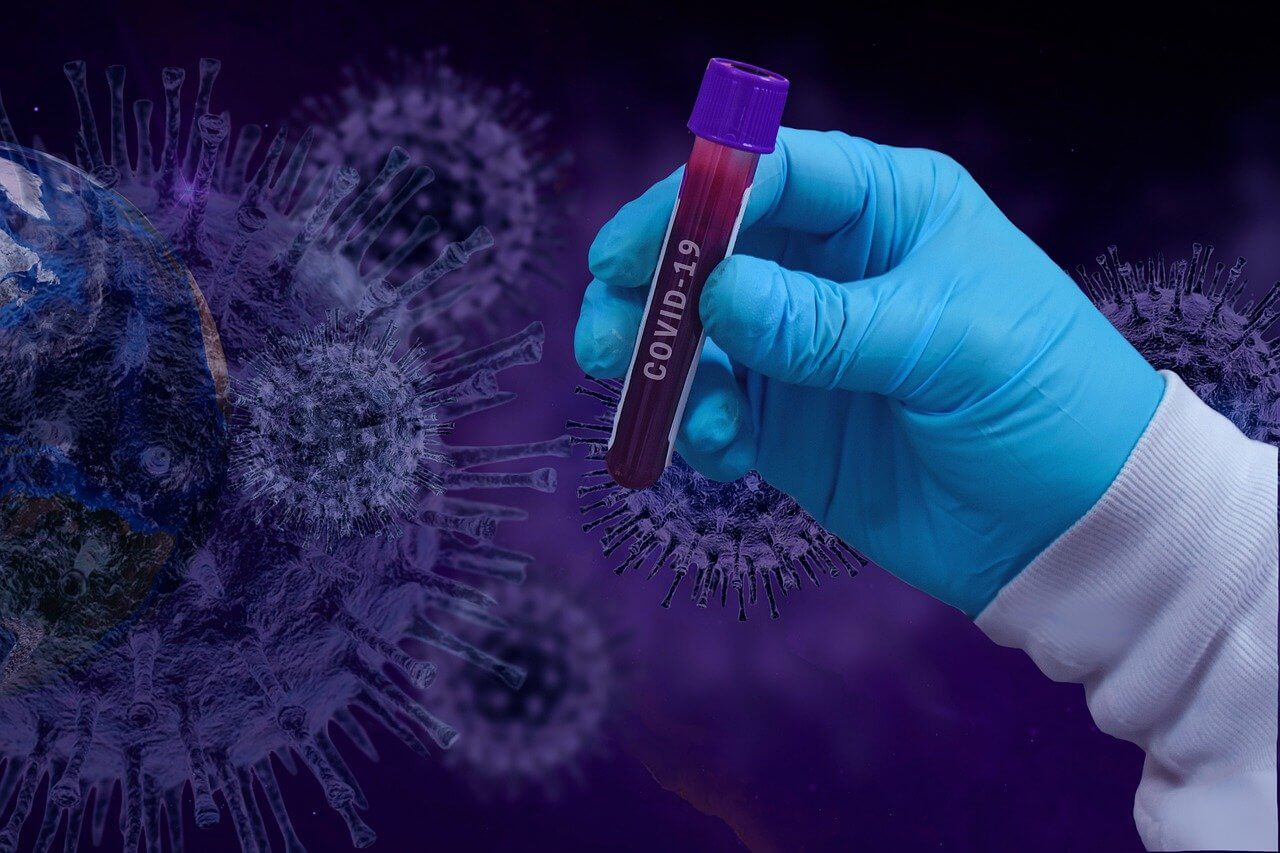2020年9月25日現在、論理学・現象学の売れ筋ランキングで1位を獲得している LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界。

SNSなどで広告を目にした人もおられるのではないでしょうか?

そんなLIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界の原著であるのデビット・シンクレア教授の ”LIfespan: Why We Age – and Why We Don’t Have to”の感想と要約をお伝えいたします。
「LIfespan: Why We Age – and Why We Don’t Have to」は直訳すると「寿命ーなぜ私たちは歳を取り、そしてなぜなぜ歳をとる必要がないのか」は、ハーバード医学部教授であるデビッド・シンクレア氏が執筆したノンフィクションの本です。
Amazon:LIfespan: Why We Age – and Why We Don’t Have to
この本では教授の生い立ちやこれまでの研究半生、そして健康的に長寿であるために私たちが何をすべきなのか?が具体的で根拠のある文章で書かれています。
今回は「LIfespan: Why We Age – and Why We Don’t Have to」のレビューを通して日本の超高齢社会を生き抜くためのヒントを見つけていきたいと思います。

Index
著者デビッド・シンクレア教授の紹介
本の著者であるデビッド・シンクレア(David Sinclair, PhD, AO)氏はハーバード大学医学部の教授であり、同世代を代表する科学分野の革新者のひとりです。
著名な科学雑誌である「Nature」や「Science」「Cell」などにも数多くの論文を執筆している文字通りの超一流の研究者であり、老化や長寿の研究分野で世界を牽引しています。
教授はTime誌で「世界で最も影響力のある100人の一人」や「ヘルスケア分野で最も影響力のあるトップ50人」に選ばれており、業界で非常に影響力を持っている人物です。
教授が問題提起していること
教授は
長寿が現代社会にどのような影響を与えるのか
今の地球環境の問題点とこれから直面するであろう危機にどのように人類が向かい合わなければいけないか
など非常に興味深い議論を展開しています。
先を見通した考えは教授の研究が単に夢物語ではなく、本人自身が研究を通して実現可能であることを肌で感じているからに他なりません。
これまでの研究結果から見える具体的な将来のビジョンは、人類が夢にみた未来がまさに現実のものになることを確信させてくれます。
教授が注いできた研究への原動力は「哀れな死に対する疑問」と「彼の家族への愛」によるものであると、本を読み進めるにつれてより強く感じられるはずです。
寿命とはただ単に生かされているだけの状態ではない
普段の生活を送っているときに死を意識することはほとんどありません。
死はいつかは誰もが必ず経験するものですが、なぜか死は遠い遠い未来のように感じます。私たちが自分の死をこれほどまでに意識しなくなったのは、世界的に見ても人類の寿命はこれまで以上に長くなっているからにほかなりません。
しかし寿命が長くなったとはいえ、それは決して良い状況になったとはいえないのではないでしょうか。寿命が長くなったことで得られた時間に生きる価値はあるのか、そんな疑問も頭をよぎります。
あなたがもし長寿を手に入れたときに現実として訪れるかもしれない未来を想像してみてください。人工呼吸器と日々の大量の服薬、骨折した腰にオムツ、化学療法と放射線療法、繰り返される手術…そしてそこまでして手元に残るのは病院から来る多量の請求書だけです。
ただ生かされているだけではそれを長寿と呼ぶことはできません。そんな状態は寿命によって生かされているのではなく、単に「生命」と呼ぶにふさわしい状況だと本の中で教授は嘆いています。
寿命が延びるのと引き換えに老化する人間

私たち人間は寿命が長くなるのと引き換えに体は加齢とともに老化していきます。人間の体は完璧ではないものの高度な生存回路を持っていて、子孫を残す生殖年齢を超えてもなお何十年も生き続けることができるのは周知の事実です。
このような体を手に入れてきた背景には、人間の遠い祖先である生物が原始の地球の壮絶な環境から生き延び、たくましく進化を繰り返してきた流れがありました。私たち誰もがこのような厳しい環境を生き延びた生命の遺伝子を受け継いでいるのです。何十億年という途方も無い年月を経てきた偉大な生存者の長い血統の子孫になるわけです。
しかしそのような生命の強い遺伝子を引き継いてきたとはいえ、現代のように寿命が長くなれば体の老化を避けることはできません。
人間の体はなぜ老化するのか
人間の体はなぜ老化するのか考えたことはあるでしょうか。なぜ老化するのかこれまでまったく考えたことがなかったとしてもそれは普通のことです。なぜなら多くの生物学者も考えたことがなかったからです。
一方で一部の科学者たちはどうすれば老化に抗うことができるのかを長年考え、研究を重ねてきました。
今日の老化に対する研究は1960年代のがん研究の黎明期と同じような段階にあるといえるでしょう。かつては運命として受け入れられてきた病気も今や毎年何十億ドルもの研究費が注ぎ込まれ、その成果としての結果が出てきています。これまでは致命的と言われたがんの生存率も劇的に上昇しているのもその最たる証拠です。
これらのがんをはじめとする病気の研究と同じように老化の研究も進み、老化とはどのようなもので私たちの体にどう影響するのかについての確固たる理解が得られています。
何が老化を引き起こすのか、老化を持続させるメカニズムも明らかになってきました。今ではがんを治すよりも老化を抑える方がはるかに簡単であると考えられてきています。
寿命のメカニズムは酵母の研究から始まった
シンクレア教授は酵母のサーチュイン遺伝子である「sir2」が酵母の遺伝子を守り、さらに老化を抑えていることをを発見しました。本書ではその経緯が詳細に述べられており、研究で十分に寝られない日々が続いていたことが手に取るようにわかります。
実は寿命のメカニズムの解析は酵母から始まったのをご存知でしょうか。
酵母はビールやワインの醸造に用いられる身近な微生物です。このとても小さな生物は外見上は私たち人間とまったく異なりますが、細胞の中の構造は驚くほどよく似ています。そのため酵母研究のおかげで人間の細胞の多くの機能が明らかになってきたのです。
酵母研究での様々な発見によって線虫やショウジョウバエ、そして人間でも長寿に関わる遺伝子が次々と発見されました。これらの発見の重要性は多くの研究で証明されています。
サーチュイン遺伝子は老化の原因となる様々な病気から体を保護する
サーチュイン遺伝子とは何か気になる方もいるでしょう。
サーチュイン遺伝子は老化の主要な要因となる以下のような多くの病気から、人間の体を保護している遺伝子といわれています。
・糖尿病
・心臓病
・アルツハイマー病
・骨粗しょう症
・黄斑変性症
・がん など
マウスの研究ではサーチュイン遺伝子を活性化することで、DNA修復能力の向上や記憶力の改善、運動持久力の向上のメリットが見られ、さらに何を食べても痩せた状態を維持することができることが分かっています。
驚くべき結果はサーチュイン遺伝子の影響についての推測ではありません。少なくとも現時点では動物では、検証されています。
加齢が病気の危険因子になる
老化は現時点では病気として診断される段階にはありませんが、老化そのものを病気として考えようという動きが本格化しています。
多くの人が高齢になるとひとつの病気だけでなく、以下のような多くの病気に苦しむようになります。
・心臓病
・がん
・関節炎
・アルツハイマー型認知症
・腎臓病
・糖尿病 など
大切なポイントは、これらすべての病気にとって加齢が病気の危険因子になるということです。
寿命を延ばすにはどうすればいいのか

人間が歳を取っていくことは避けられません。しかし誰もがなるべく病気にならずに健康的に寿命を伸ばしたいと願っています。実は寿命を延ばすライフスタイルは既にいくつか知られています。
それらを本書では以下のように説明しています。
栄養制限や運動でNADを増やす
摂取する栄養を制限することや運動を行うことで、体に備わっている「サバイバルスイッチ」をオンにさせることが効果的とされています。
つまり栄養の制限や運動によってミトコンドリアでのエネルギー産生反応の補因子であるNAD(ニコチンアミドアデニンヌクレオチド=nicotinamide adenine dinucleotide)を増やし、サーチュイン遺伝子を活性化させるのです。このNADは加齢とともに減少していくため、意図的に栄養の制限や運動を行うことが必要になります。
寒さに体をさらしてサーチュイン遺伝子を活性化させる
暑さ、寒さなど過酷な気温に体をさらすことでサーチュイン遺伝子を活性化させることもできます。
例えば寒さがミトコンドリアを活性化しますがこの時、熱を生成し、その結果NADが作り出されてサーチュイン遺伝子が活発になります。それによって糖尿病や肥満、アルツハイマー型認知症のリスクを減らすことができるのです。
DNAのダメージを最小限にする
サーチュイン遺伝子を活性化させるにはDNAのダメージを最小限にすることも重要です。なぜならサーチュインを活性化させるNADはDNAダメージを修復する酵素も使っているため、ここで大量に消費されてしまうからです。
糖尿病薬のメトホルミンに寿命を延ばす効果がある
ヒトでの寿命延長効果が期待され、確かめられようとしている薬があります。それが糖尿病の薬として知られている「メトホルミン」です。
世界中で糖尿病に対して最も広く使用されており、効果があるといわれている薬のひとつであるメトホルミンは、研究においてマウスの寿命の延長させるだけでなく、ヒトでもLDL(悪玉コレステロール)を減少させ、身体機能の亢進やがんを予防する効果があることが数多くの研究により明らかになっています。
メトホルミンは間接的にサーチュイン遺伝子を活性化させます。またメトホルミンの服用による副作用もまれに見られる乳酸アシドーシス(乳酸が過剰に蓄積して起きるアシドーシス)と胃部不快感のみで、通常の服用量では月に5ドル程度しかかからないといった点も安全性やコスト面において優れた薬だといえるでしょう。
レスベラトロールの発見
世界ではサーチュインの遺伝子を活性化させる化合物の探索が始まり、ついに世界的にも有名になったレスベラトロールの発見につながりました。
レスベラトロールが発見された経緯も本書では詳しく記載されており、非常に興味深い内容になっています。
現在ではレスベラトロールと比べてサーチュイン遺伝子を何倍も活性化させる効果がある物質も見つかっており、ヒトでの試験が行われています。
NADを増やすにはどうすればいいのか
サーチュイン遺伝子を活性化させる分子であるNADを増やすにはどうすればいいのでしょうか。
NADを細胞に取り入れるのはとても難しいとされているものの、体内でNADに変換される分子が発見されています。
体内のNADを増やす物質として「ニコチンアミドリポシド(NR=nicotinamide riboside)」と「ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN=nicotinamide mononucleotide)」が紹介されています。
この2つの分子はマウスの研究で高齢マウスの身体機能を若返らせることが分かっています。さらに寿命の延長に関してNMNは試験中となっているものの、NRはマウスの寿命を延長させることも分かっているのです。
これらの分子が人間に与えるメリットについては、今まさに臨床試験が行われているところです。
本書では老化を抑える上述のこと以外にも、老化した細胞を体から排除することの意義やその方法などにも言及されており、これまで知られている老化に関わる最先端の情報が網羅されています。
iPS細胞技術の応用で老化した細胞を若返らせることも可能?
本書では山中伸弥教授が発見したiPS細胞についても触れられています。
iPS細胞の技術は体細胞を多能性幹細胞に変化させることであり、まさにiPS細胞の発見はディッシュ上で細胞を若返らせることができることを実証しています。
この技術を応用することで人の体内でも細胞を若返らせることが可能になるかもしれません。将来、サーチュインをサプリメントや薬で活性化したり、iPS細胞の技術を応用して体内の細胞を若返らせることができれば、老化を制御する未来が現実になることを予感させてくれます。
多くの科学技術の応用で今後さらに寿命が延びる
今後は多くの科学技術の応用によって寿命がさらに伸びると予想されています。
ここまで述べてきた遺伝学的なアプローチだけでなく、生体分子を識別できる分析装置である「バイオセンサー」の発達によって未然に病気を捉えることが可能になるでしょう。
さらに遺伝子の配列を分析するシークエンス技術の進歩によって、個人によりフィットした薬の提供や栄養学的なアプローチの進歩なども期待できます。これらの多くの科学技術の進歩と応用により寿命や健康寿命がさらに伸びることが予想されています。
それでは長寿を達成した社会にはどのような未来が待っているのでしょうか。
社会構造が大きく変わり、地球温暖化による気候変動も引き続き起こり、人口爆発が社会インフラに大きく影響を与えていくはずです。これからの社会が待ち受ける変化や様相が非常にリアルな形で述べられているのがとても印象的です。
本書で述べられている考察の根底にはシンクレア教授自身が老化に打ち勝ち長寿を手に入れるという自信があり、研究者としてその責任を感じていることが文章を通じて強く伝わってきます。
シンクレア教授が摂るサプリメントとは?
これほどの内容の本を執筆したシンクレア教授が実際にどんな生活を送り、どのようなサプリメントを摂取しているのか誰もが非常に気になるところです。
本書で紹介されているレスベラトロールやNR、NMNは実際にサプリメントとして一般に販売されており、教授自身も1日に50回も「どんなサプリメントを摂取すればいいのか?」と聞かれるそうです。
ここでは教授が薦めるサプリメントやサプリメントの選び方、日常的に摂取しているサプリメントの種類などが紹介されています。教授自身が毎日どんなサプリメントをどれだけ摂っていて、生活では何に気をつけているか非常に気になる内容となっています。是非本書で内容を確認してください。
教授が本書を執筆した時は50歳でしたが、白髪や顔に見られる深いシワもなくまさに健康そのものです。さらに心臓の機能は30歳と変わらないというのも驚きです。教授の父親もほぼ同じ内容のサプリメントの摂取や生活を続けているためか、日々とても活動的に過ごしている様子についても紹介されています。
教授が抱く老化を防ぐ研究に対する自信と本書に見られる説得力ある解説に、読者は自分の未来のために今何をするべきなのかを考えさせられるでしょう。そして未来に存在するであろう100歳を超えた自分の姿を容易に想像させてくれる、そんな力がこの本にあると誰もが感じられるに違いありません。