この秋は、「他の人と自分を比べる」ことをテーマにした取材や仕事が続きました。
自分を振り返ってみても、学生時代には成績や友人関係をクラスメイトと比べたり、大学院では研究の進捗を同級生と比べたり、就職してからは、仕事結婚出産などのライフステージを比べたり、そのときどきの自分にとって大事なことを人と比べていたように思います。
ようやく最近、「自分は自分」と自然に思えるようになり、人と比べる機会が減ったように感じていましたが、新たに子育てが始まり、他のおうちではどうしてるんだろう⁈とまた、周りのことが気になることが出てきました。
社会的比較
この「他者と自分を比べる」現象は、心理学では「社会的比較」と呼ばれて、社会心理学の領域で研究されてきました。
私たちが他者と自分を比べるのには、理由があって、一概に悪いことというわけではなく、一定の機能を果たしています。
1つ目の機能は、「自分のことを正しく理解したい」という欲求を満たすためです。
「自分は〇〇が得意」というのも、人と自分を比べて初めて気づけることだったりします。
2つ目の機能は、他者を見て新しいことを学んだり、社会的な規範やルールを身につけることです。
私の2歳の娘も、保育園でひとつ上のクラスの友達を見て、おもちゃの遊び方を覚えたり、散歩のときに危なくないようにみんなで手をつなぎあったり、周りを見て行動しています。
3つ目の機能は、自尊心を守る機能で、自分が苦しいときに「もっと大変な人もいるのだから、自分はまだ大丈夫」と言い聞かせたり(これだけ聞くと嫌な感じかもしれませんが、それで心を守れることもあります)、自分より少し優秀な人や幸せな人と見比べて、「あの人みたいになれるように頑張ろう」と思うことで、自尊心を高めようとしたりします。
「他者と自分を比べる」というと、よくないことのように聞こえるかもしれませんが、ここで紹介したように、私たちにとって、大事な機能・役割も果たしているのです。
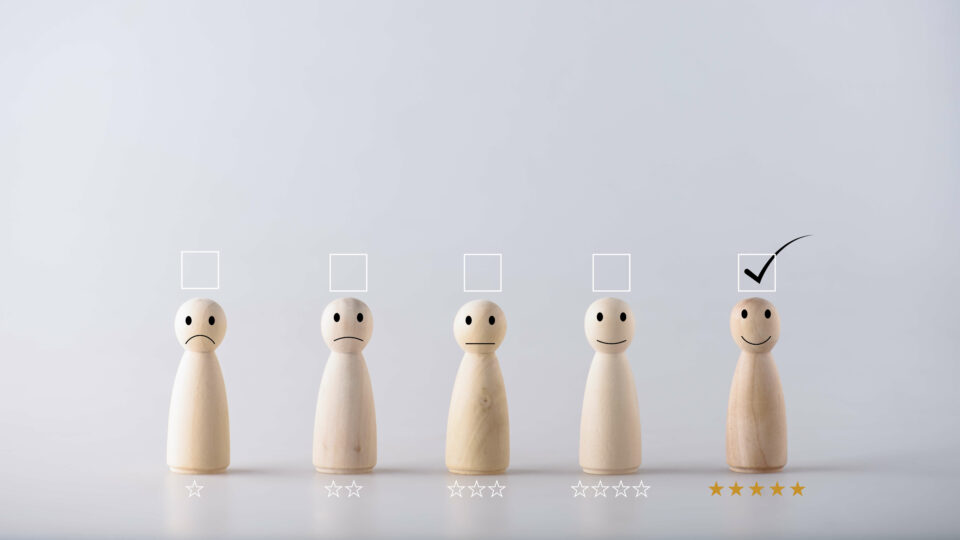
他者と自分を比べることで、苦しくさせてしまうこともある
ただ、時に、他者と自分を比べることが、私たちをさらに苦しくさせてしまうこともあります。
つらいとき、しんどいときに、そのつらさやしんどさを他者と比べて、「自分の努力や我慢が足りない」、「みんなも頑張ってるのだから、自分ももっと頑張らなければいけない」と自分に鞭打ってしまうのです。
ただでさえ苦しいときに、さらに自分を追い詰めてしまうのです。
しんどさ・苦しさというのは目に見えないものです。
身体面のことであれば、熱が〇度ある、出血している、腫れているなど、目に見えてケアする必要性がわかることもあるのですが、目に見えないしんどさ・苦しさは、つい我慢したり、後回しにしてしまいがちです。
そこでさらに、「他の人はもっと頑張っている・我慢している」と比べてしまうと、休んだり、自分をケアするきっかけを失くしてしまいます。
「つらい」と認めてあげていい
自分が「つらいな、しんどいな」と感じたら、それはもう、「しんどい」でいいし、「つらい」と認めてあげていいと思うのです。
そして、それを自分に対しても家族や友人や同僚をはじめ、誰かに対しても認められること、ここからセルフケアが始まっていくのだと思います。
【参考文献】
他者と比べる自分-社会的比較の心理学. (2011). 高田利武. サイエンス社.





















