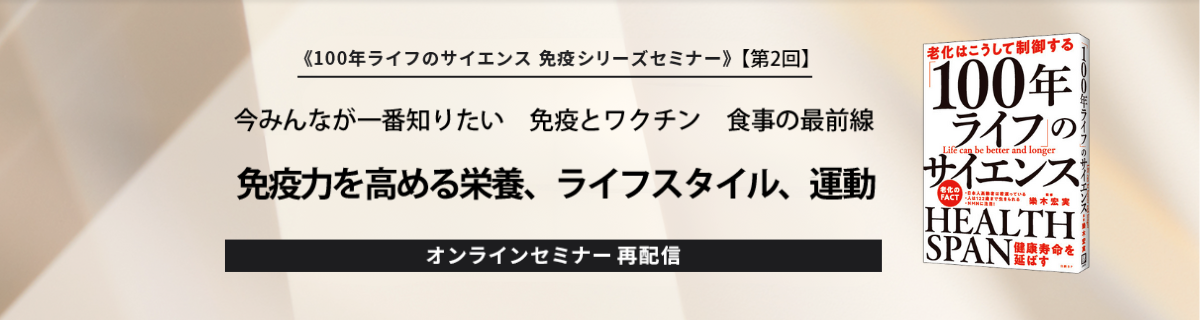最近、「希望」ってパワフルだな、と実感する出来事がありました。
70歳になろうという母が心不全でCCUに入ったのですが、その経緯には、心臓の問題よりも、気持ちの問題が影響していました。
CCUに入ることになる数日前から不調を感じていた母。
電話でそれを聞いた私は、受診を強く勧めたのですが、気が進まない様子で、その翌週の定期受診からそのままCCUに入院することになりました。
あとで話を聴いてみると、こうぽつりとつぶやいたのです。
「もういいかな、と思って」
60年も心臓の病気と付き合ってきた母の本音だったと思うのですが、娘としてはやはりショックでした。
そんな母が退院するときには、すっかり明るい顔になっていました。
新型コロナウイルス対策で入院中の面会は叶わなかったので母からの話で知ったことですが、どうやら一般病棟に移ったあとに同室になった方たちが猛者ぞろいだったようなのです。
ひとりは、89歳で心臓の手術を受けたという方、もうひとりは心臓移植の手術を受けた方だったのです。
私が小さいころから「60歳までなんて、とても生きられない」、60が見えてきてからは
「70歳まで生きるなんて、とても無理」が口癖だった母も、これには驚いたようです。
平均寿命を超えてなお、心臓の手術が受けられる。
医学の進歩が目覚ましいなと思うと同時に、手術を受けようと決めた、その方の意志と気力と、その背後にあるであろう家族のサポートをひしひしと感じました。
母も直接話を聴いて、同じ部屋で一緒に生活をして、それを体感したのだと思います。
そこで思い出したのが、ポジティブ心理学の研究室に在籍していた大学院時代に出会った「希望」という概念でした。
当時は、なんだか壮大で、捉えどころがないなと思っていましたが、心理学の研究で取り扱われている「希望(ホープ)」について、改めて調べてみました。

Snyderという研究者が提唱している希望理論によると、目標(Goals)、目標指向的計画(pathways thought)、目標志向的意志(agency thought)の3つの構成要素があります。
希望は、目標に向けて、目標指向的計画と目標指向的意志が相互に関連し合う思考プロセスのこと、と定義されているようです。
目標指向的計画は、目標に到達するための道筋を見出す能力とされていて、自分が目標を達成するための方法をたくさん見出すことができると信じていて、達成を妨げる障害が出てきたとしても、別の道筋を見出すことができる力です。
目標指向的意志は、目標達成に向けて思い描いた計画に沿って行動を起こして、それを継続するための能力で、障害が出てきたとしても、前向きなエネルギーを計画に向けることができるとされています。
前者が目標達成までの道筋をつくる能力で、後者がその道を歩むための動力になるといえます(図)。

調べてみて、私も改めて感じましたが、私たちが日常的に使う「希望」のイメージとは違っています。
(ちなみに、広辞苑第5版によると、「希望」は、「①あることを成就させようとねがい望むこと。また、その事柄。のぞみ。②将来によいことを期待する気持ち。」とされています。)
私が意外に感じたのは、「希望」が認知プロセスと位置づけられているのだ(気持ち・感情ではなく)ということと、目標達成するうえで「障害」があることが理論の中で想定されているという2点でした。
特に2点目の意味で、「希望」はさまざまな困難な状況に立ち向かっていく推進力なのだといえます。
「希望」が高いほど、ストレス反応、絶望感、特性不安、抑うつが低く、精神的健康がよいことが示されているのも納得です。
一方で、この「希望」の考え方が、「自分は、目標を達成する道筋を見出すことができる」、「障害が出てきても、別の道筋を見出せる」、「障害があっても、目標達成に向けて前向きなエネルギーを出せる」といった具合に、自分への信頼感だけに裏打ちされているようで、そこには偏りがあるようにも感じました。
退院してきた母の姿を見て、「希望」を支える土台には、自分への信頼だけでなく、自分以外の人間や、この世界そのものへの信頼、未来への信頼もあると感じました。
自分の中に「希望」があるとすれば、それは自分だけで育てたものではなく、人や世界との関係の中で育ってきたものなのでしょう。
自分の中の希望の源泉を見つけて、周りの人やこの世界とのつき合い方に目を向けてこそ、希望という力は育っていくものなのかもしれません。
【参考文献】
・Snyder, C.R. (2000). The past and possible future of hope. Journal of Social and Clinical Psychology,19 (1),11-28.
・Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13, 249-275.