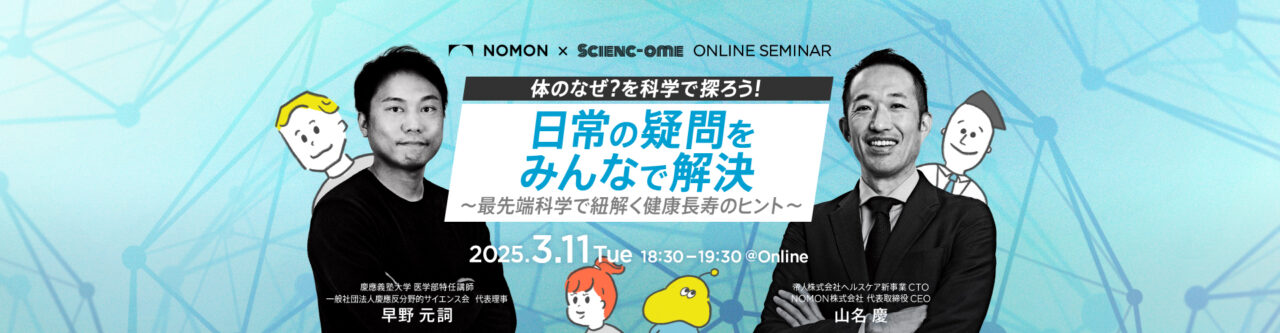「認知機能」とは、ヒトがもつ脳機能のひとつであり、私たちがこの世界の中で生きていくために必要な学習や記憶、知覚などに分類されます。しかしながら、認知機能はある程度の年齢になると衰えていくことも知られています。この記事では、認知機能の概要と加齢による変化、高齢者の認知機能および行動の特性について解説し、近年明らかとなった認知機能改善効果をもつ成分について紹介します。
Index
認知機能とは
「認知機能」という言葉は、一般的には認知症の障害の程度を表す際に用いられることが多いですが、実際には判断、理解、論理などの知的機能のことを指しています。※1
認知機能は、「ものごとや外界を正しく理解し、適切に実行するための機能」と定義されることもあります。つまり、自分の周囲をとりまく世界から受け取った情報や刺激を認識・理解して、行動を起こし成し遂げるまでの脳のはたらきを指します。※2、3
なお、「認知」とは、精神医学的な視点では「知能」という言葉の意味に近いといえます。心理学的な視点では、「知覚」を中心にした要素(判断・決定・推論・想像・記憶・決定・言語理解など)を包括したものを「認知」ととらえています。※1
認知機能の分類
日本精神神経学会は、認知機能を次の6つの領域に分類しています。※4
| 複雑性注意 | 持続性注意、分配性注意、処理速度 |
|---|---|
| 実行機能 | 意思決定、ワーキングメモリー、フィードバック |
| 学習と記憶 | 即時記憶、近時記憶、長期記憶 |
| 言語 | 表出性言語、受容性言語 |
| 知覚-運動 | 視知覚、視覚構成、知覚-運動、実行、認知 |
| 社会的認知 | 情動認知、心の理論 |
これらの領域がさまざまに関与しあって、私たちは日常生活を送ることができています。例えば、「歩く」という運動の場合、「たくさんの人達が歩く場所でぶつからないようにする」ためには、向かってくる相手の速度を計算して避けたり、自分の前をゆっくり歩く人を時間や空間を計算した上で自分の速度を上げて追い抜いたりといった行動をします。単純に見える運動(行動)でも、認知機能なく成立させることはできません。※4
加齢による認知機能の低下
さまざまな認知機能のなかでも、人の名前を思い出せない、新しいものごとを覚えられないといった記憶に関する変化は、加齢による認知機能の低下を意識するきっかけになります。そもそも、起こったできごとがどのようにして記憶されるのか、記憶のメカニズムについて考えてみましょう。
記憶のメカニズム
感覚器から入力された情報は感覚記憶として取り込まれ、その中でも意識(注意)を向けられた(注意)情報が、短期記憶として脳内に保存されます。忘れ去られる記憶もありますが、必要な情報は短期記憶のなかで反復され、長期記憶として保持されます。※5
長期記憶は、記憶の内容を思い起こし意識上に取り出せる陳述記憶と、取り出せない非陳述記憶に分けられます。さらに、陳述記憶には意味記憶とエピソード記憶(経験したことに関する記憶)などが、非陳述記憶には手続き記憶があります。※6、7
このなかでも、短期記憶や長期記憶のうちエピソード記憶は、加齢によって低下しやすいとされています。短期記憶の機能低下は、いわゆる「もの忘れ」とよばれる状態です。※8
一方、言葉の意味や概念などの意味記憶、体で覚えた記憶などの手続き記憶は、年齢を重ねても低下しにくいとされています。
記憶のメカニズムについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:記憶のメカニズムとは?短期記憶と長期記憶の違いについて解説
脳の萎縮
認知機能の低下には、加齢に伴う脳の萎縮が関わっています。脳が萎縮するスピードは、部位によって異なることが知られています。一般的には、前頭葉、側頭葉が萎縮しやすく、後頭葉は萎縮しても軽度となる傾向にあります。高齢者の脳萎縮を組織学的にみると、前頭葉皮質の層構造や機能は保たれるため、情報処理量の低下による発動性の低下や思考の緩慢化といった症状が現れます。※9
なお、前頭葉が萎縮して起こる前頭側頭型認知症では、皮質上層の神経細胞の萎縮や消失、層構造の欠落によって情報伝達経路の脱落がみられ、大きな障害が出ることがわかってきました。また、病理学的な変化として老人斑や神経原繊維変化もみられます。こうした変化はアルツハイマー病だけでなく一般的な加齢脳にもみられますが、一定範囲内の出現は生理的発現とされ、大量または広範囲にわたる蓄積の場合は疾患とされています。※9
脳のサイズは20代でピークを迎え、そこから徐々に萎縮します。年代別にみると、60代で5~10%、80代では10~20%委縮するとされています。脳の萎縮は神経細胞の数の減少が原因と考えられており、結果として「脳の処理能力の低下」が起こります。これがいわゆる認知機能の低下であり、50歳頃から始まることが多いようです。※2
認知機能が低下する年代については、株式会社エス・エム・エスが提供する「認知機能チェック」のデータ分析でも明らかになっています。「認知機能チェック」は、認知機能を記憶力、言語能力、判断力、計算力、遂行力の5つに分け、それぞれに対応する問題を解く形式の、5分ほどでできる簡単なチェックツールです。
2016年の提供開始から2018年までにこのチェックを受験した累計16万人を分析した結果、50歳頃から認知機能が徐々に低下し、55歳頃からは明らかな低下傾向になることが示されています。※10
しかしながら、知能面ではマイナスの変化しかないわけではありません。さまざまな研究を通して、語彙力が80代になっても維持されていることや、知識力が70歳頃まで向上することなどが示されています。また、年齢に応じた方法で学習を進めることで、知的好奇心を満たし続け、豊かな生活が可能になります。
学習効果と老化の関係について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:学習効果と老化の関係とは?加齢による知能の変化について解説
高齢者の認知機能の特性と行動特性

前述の通り、加齢によって認知機能は低下していきますが、すべての機能が完全に失われてしまうわけではありません。なかには機能低下のスピードがゆるやかで、高齢になっても比較的維持される能力もあります。※11
また、認知機能の低下というといわゆる「認知症」を思い描くかもしれませんが、実際には正常な認知機能、認知症の前段階であり生活には支障がないMCI(軽度認知障害)、認知症は明確に区別されるわけではなく、グラデーションのようにつながっています。特に、MCIは環境などさまざまな影響を受けることで、認知症と正常な状態をいったりきたりします。さらに、認知症やMCIではない高齢者にも、認知症の原因とされる動脈硬化、小さな脳梗塞、微小な脳出血、脳への異常なタンパク質の蓄積などが起こることは珍しくありません。※11
このように、加齢による認知機能の低下は誰にでも起こり得ます。維持される能力にも目を向け、高齢者が持つ多様な可能性に理解を深めるとともに、認知機能の低下によってどのような行動特性があるのかを知り、その心理や不安を社会で理解することが大切です。※11
具体的には、加齢に伴う認知機能の低下などによって、次のような行動特性が強まる傾向にあります。※11
注意力を維持するのが難しくなる
- いつもの作業に時間がかかるようになる
- 何度も確認することが多くなる
- ケアレスミス(鍋の空焚きなど)が目立つようになる など
数秒間、頭の中での情報を保ちコントロールすることが難しくなる
- 会話についていくことが難しくなる
- 簡単な計算や暗算が難しくなる
- 同時に複数のことをするのが難しくなる など
数分~数時間内の個人的なことに関する記憶力が低下する
- 片づけた場所が思い出せず、探し物が多くなる
- 支払いを済ませたかどうか思い出せなくなる
- 繰り返し同じものを買ってしまう など
耳からの言葉の意味の理解が難しくなる、流暢な言葉が出にくくなる
- 長い話や複雑な説明だと内容が理解できない
- 人や物の名前が出てこず、「あれ」「それ」などが多くなる
- 質問内容が理解できず、会話がかみ合わなくなる など
位置・方向・距離の感覚がとらえにくくなる
- 建物の中でも迷いやすくなるため、目的地にたどり着けなくなる
- 交差点で正しい道がわからなくなる
- 自分の居場所がわからなくなる など
情報の整理、計画、意思決定というプロセスの実行が難しくなる
- 段階的な操作が必要となる機械(券売機、ATM)を使うことが難しくなる
- 予算の見積もりや適切な金銭管理が難しくなる
- 説明や表示の誘導によって、不要なものを購入してしまう など
自己の行動による結果を予測しにくくなる
- 自信過剰になり、詐欺被害にあいやすくなる
- 望ましくない選択や自己に不利な選択をしてしまう
- 自己に不都合な情報には注目せず、都合のよい情報を記憶する傾向があり、適正なリスク評価ができない など
意欲・自発性が低下する
- 日常的な外出(買い物など)が減り、閉じこもりがちになる
- 人とのコミュニケーション、新しいものごとや技術、社会活動を避けるようになり、孤立しがちになる
認知症

認知症とは、脳の細胞死や機能低下のために起こるさまざまな障害(病気)によって、記憶や思考など認知機能がだんだん低下し、およそ6ヶ月以上継続して生活に支障が出ている状態のことをいいます。※12
内閣官房ホームページにて公開されている、九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野の二宮利治教授がまとめた報告によると、国内の認知症患者数推計値(95%信頼区間)は2022年で443.2万人、有病率(同)12.3%と推計されています。この報告では2060年までの5年ごとの将来推計を算出しており、2040年には584.2万人(14.9%)、2055年には616.0万人(16.3%)が認知症となるとしています。※13
アメリカ精神医学会(APA)による認知症の診断基準「DMS-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5))では、以下の6項目のうち1つ以上で認知機能障害がある場合に認知症と診断されます。これは、前述の日本精神神経学会による認知機能の領域に重なります。※14
- 複雑性注意
- 実行機能
- 学習と記憶
- 言語
- 知覚-運動
- 社会的認知
認知症の原因
認知症の原因となる病気は、大きく次の2つに分けられます。※12
脳の神経細胞死が少しずつ進んでいくもの(変性疾患)
アルツハイマー病、前頭・側頭型認知症、レビー型小体病
神経細胞に酸素や栄養が行き渡らないために起こる神経細胞死や神経ネットワーク破壊
脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などの脳血管性認知症

認知症の症状
認知症の症状には、脳細胞の破壊によって直接現れる中核症状と、環境・性格・人間関係などさまざまな要因が関わって現れる周辺症状があります。中核症状としては、記憶障害、理解・判断力の障害、見当識障害、実行機能の低下などが挙げられます。これらの症状により、自身の周囲で起こる現実を正しく認識できなくなります。周辺症状としては、徘徊、興奮・暴力、不潔行為などの行動上の問題や、うつ状態、幻覚・妄想、せん妄など精神状態がみられ、日常生活への適応を困難にしてしまいます。※12

認知機能を改善させる方法

認知機能の低下は、誰にでも起こり得る変化です。また、生きている限り、誰にも加齢を止めることができないのも事実です。その一方で、近年はさまざまな研究が進められており、認知機能を改善できる可能性を秘めた成分も見つかっています。
例えば、薬味として食卓にあがることの多いわさびには、「わさびスルフォラファン」とよばれる独特な成分が含まれています。
抗酸化・抗炎症作用が強い成分として知られていますが、人間環境大学の野内類教授と東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授を中心とする研究グループにより、わさびスルフォラファンの長期摂取には記憶機能の改善効果がある可能性が報告されました。報告の中では記憶機能の改善の仕組みとして、脳の部位である海馬における酸化物質や炎症とわさびスルフォラファンのもつ抗酸化・抗炎症作用の関連を考察しています。※15
わさびスルフォラファンについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:わさびスルフォラファンで記憶力が向上?臨床試験の概要を紹介
さらに、強い抗酸化作用をもつわさびスルフォラファンと相性の良い成分として、認知機能改善などの健康増進効果で知られる成分オメガ3脂肪酸(EPA、DHAなど脂肪が多い魚に含まれる脂肪酸)が挙げられます。金印株式会社の主導で行われた研究を通して、わさびスルフォラファンとオメガ3脂肪酸を併用することで神経細胞に対する効果が大きくなることが明らかとなりました。
古来より魚にわさびを添えて喫食する習慣のある日本人においては、オメガ3脂肪酸とわさびスルフォラファンの相乗効果を狙いやすいといえます。ただし、わさびスルフォラファンは擦りたての本わさびに多く含まれる希少成分であり、市販のチューブわさびでは効果が得にくいとされています。十分な効果を得るためには、サプリメントを利用するのもひとつの方法です。
オメガ3脂肪酸とわさびスルフォラファンの相乗効果について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:オメガ3脂肪酸とわさびスルフォラファンを併用すると?
認知機能の特性や加齢による変化について知っておくことが重要
加齢に伴う認知機能の衰えは、簡単に止めることはできません。しかし、認知機能の特性や、いつ頃から衰え始めるのか、どういった症状が現れるのかなどをあらかじめ知っておくことは大切です。近年では、認知機能の維持や改善といった研究も行われています。「自分の脳にとって良いこと」を探し、生活に取り入れていきましょう。
参考資料
※1 厚生労働省. e-ヘルスネット. 認知機能(にんちきのう).
※2 名古屋大学 総合保健体育科学センター. 認知機能と認知症のお話し.
※3 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所. 超高齢期の認知機能~百歳までと百歳から.
※4 中田大貴 芝崎学. (2019) 認知機能と環境ストレス. 日生気誌. 56(1) 3-11.
※5 Atkinson RC, et al. (1968) Human memory: A proposed system and its control processes. In:Spence KW, Spence JT, editors. Psychology of Learning and Motivation. 2. 89-195.
※6 畔柳圭佑.(2022) 記憶はスキル 科学的研究でわかった!人生が10倍楽しくなる記憶のルール. クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
※7 榎本博明.(2016) 記憶力を高める科学 勉強や仕事の効率を上げる理論と実践. SBクリエイティブ
※8 一般社団法人日本老年医学会. (2013)老年医学系統講義テキスト. 西村書店. 102-103.
※9 神崎恒一. (2018) 加齢に伴う 認知機能の低下と認知症. 日本内科学会雑誌. 107(12). 2461-2468.
※10 株式会社エス・エム・エス. プレスリリース. 認知症・MCI早期発見テストの利用者増加、受検者数累計16万人を突破認知機能の低下・予防意識の高まりから、受検者数は前年比約105%~認知機能は50歳頃から徐々に低下、55歳から明らかな低下傾向~
※11 東京都保健医療局. 高齢者の特性を踏まえたサービス提供のあり方検討会報告書. 第3章 高齢者の認知機能の特性と行動特性.
※12 厚生労働省. 政策レポート 認知症を理解する.
※13 内閣官房. 令和5年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」.
※14 宮崎江南病院. 認知症を知ろう ~高齢社会でいきいきと暮らす為に~.
※15 Rui Nouchi, et al. (2023) Benefits of Wasabi Supplements with 6-MSITC (6-Methylsulfinyl Hexyl Isothiocyanate) on Memory Functioning in Healthy Adults Aged 60 Years and Older: Evidence from a Double-Blinded Randomized Controlled Trial. Nutrients. 15(21). 4608